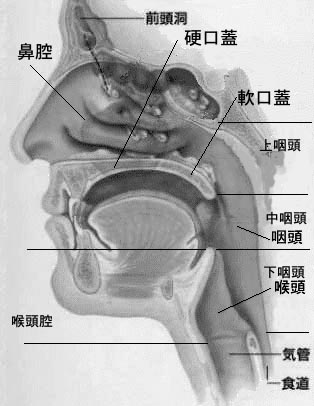
「ヴォーチェ・ディ・フィンテ」で発声してもその響きづくりが拙ければ「良い響き」として聞こえてきません。
(まぁ逆も真で、「良い響き」として聞こえてこなければ「ヴォーチェ・ディ・フィンテ」も出来てはいないということなのですが)
ということで今回は「OCM歌唱発声法」の《核》「響き」についてです。
音の元は声帯で作られる「喉頭原音」ですね。
ここで発せられる音は小さく弱い雑音です。
それを「増幅」させ、「響き」を作るのは「声帯」の上部、つまり喉頭腔・口腔・鼻腔、それに咽頭です。
それに補助的に前頭洞が加えられるかもしれません。
これらの空洞を利用して音に「美しい響き」を与えます。
まず、「響きづくり」に大きな影響を与えるのは口腔と咽頭だと知ってください。
そしてそれ以上に最も重要なところが上咽頭および鼻腔です。
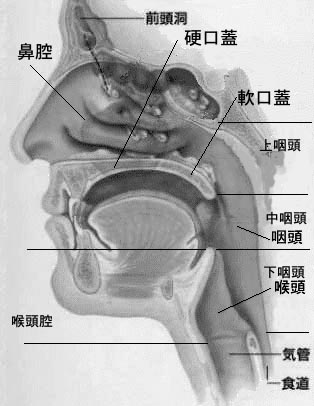
口腔は母音づくりに大きく関与します。(音色に関与)
咽頭や鼻腔は音の大きさ・深さ・広がりに関与します。
特に上咽頭および鼻腔は歌唱発声にとって重要な《響きの核》づくり貢献します。
これらの場所ではいかに効率的に《広げる》か、それが重要課題です。
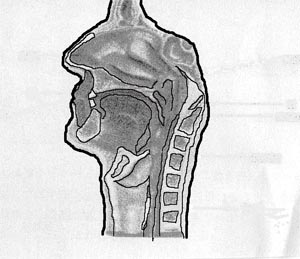

歌唱発声にとって重要なことは喉頭と連動している舌の状態です。
舌が硬くて口腔の広がりに支障をきたすばあい、充分で満足のいくような響きは得られないでしょう。
柔らかい柔軟な舌がいいですね。(口腔が広い、これは歌う者としての良い条件です)
咽頭の広げはひたすらこの部分の《広がり》のイメージにかかっています。
声をどのように飛ばし(放物線を描きます)、距離を持たせるか、そのイメージです。
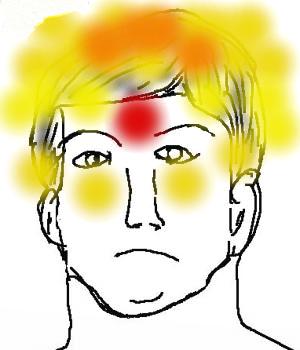
この【眉間】に《響きの核》をもってきた時、声の威力がもっとも増します。
よく飛び、声も輝き、精神的な響きというのでしょうかとにかく声が〔生きてくる〕のですね。
(ピッチが定まるのもこのポイントです!)
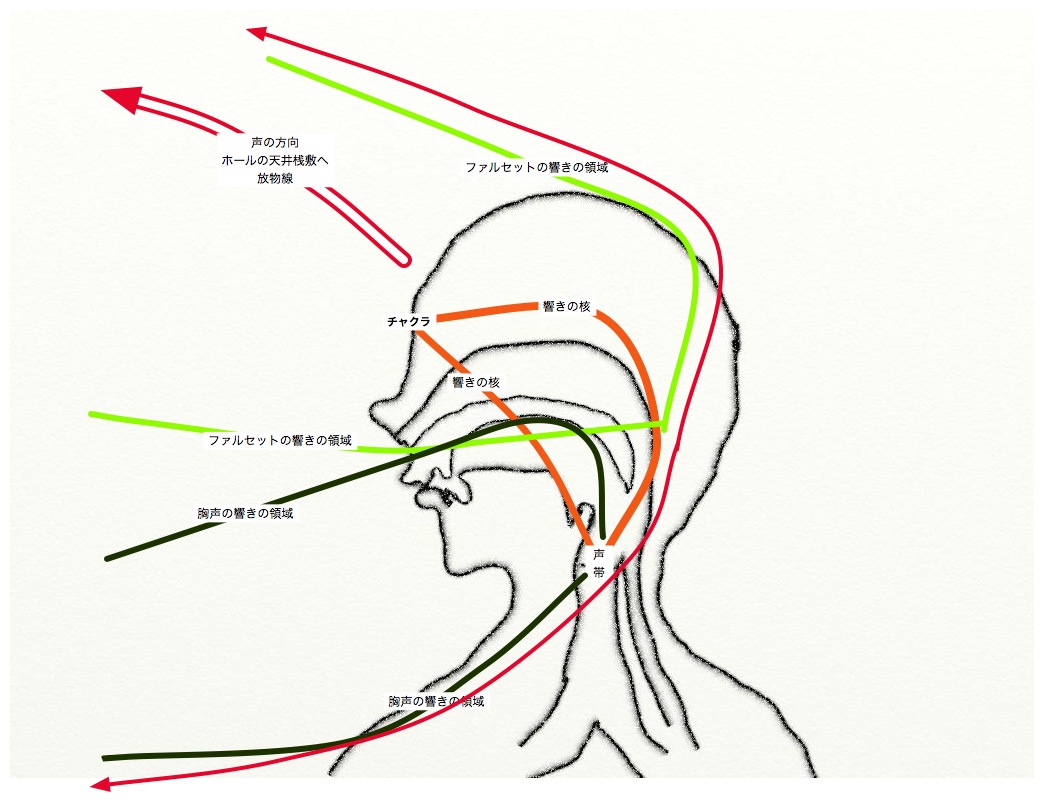
響きづくりは「自然倍音」によって作る。
それはどの領域でも共鳴し合えるということに繋がります。
そこで立ち上がる《響き》はきっと人間にとって、生きる躍動、生きる喜びを呼び覚ます大きな力となるのではないか、そう思えてなりません。
まだまだ私たちは自然の中に生かされている小さな存在です。
しかし、これらの《響き》の体験によって私たちと自然は、いや、宇宙と私たちは繋がれるんだと思うのですね。
第49回「響きの核と領域」この項終わり